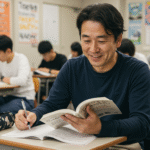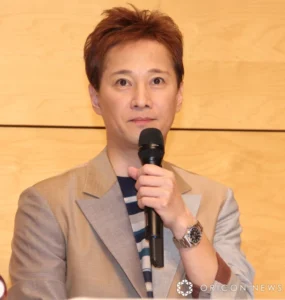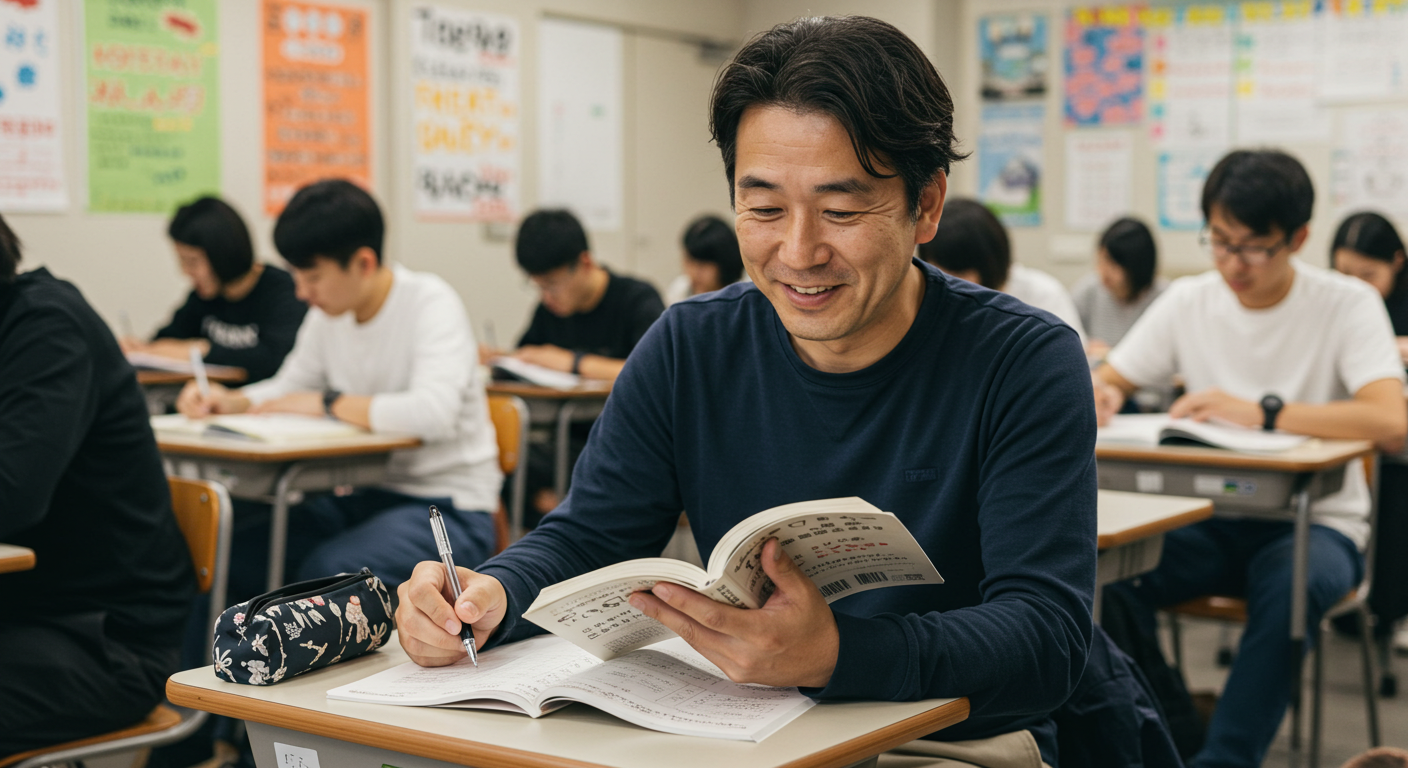
宅建士試験対策!「一身専属的権利」をわかりやすく解説
宅建士試験の勉強、お疲れ様です!民法の学習を進める中で、「一身専属的権利」という言葉を目にしたことはありますか?ちょっと難しそうな響きですが、実は日常生活にも関係の深い、とても大切な概念です。
今回は、この「一身専属的権利」について、宅建士試験で問われるポイントも踏まえながら、わかりやすく解説していきます。
一身専属的権利とは?
まず、定義から見ていきましょう。
一身専属的権利とは、その権利が特定の個人に強く結びついており、その個人だけが持っている、あるいは行使できる権利のことを指します。
つまり、他の人に譲渡したり、相続させたり、代わりに使ってもらったりすることができない権利、ということです。その人自身が持つからこそ意味がある権利、と考えるとイメージしやすいかもしれません。
なぜ「一身専属」なの?
なぜ、特定の権利は「一身専属」とされるのでしょうか?それは、その権利がその人の人格や能力、特定の関係性に基づいて発生しているからです。
例えば、
- 扶養請求権:親が子に対して扶養を求める権利、子が親に対して扶養を求める権利は、親子関係という特定の関係性に基づいています。これを第三者に譲渡することはできませんよね。
- 生活保護受給権:生活に困窮している人を保護するための権利であり、その人個人の生活状況に密接に関わっています。
- 使用貸借における借主の権利:友人から物をタダで借りる「使用貸借」の場合、貸主はその友人個人だからこそ貸したわけです。借りた物を勝手に別の人に貸す(転貸する)ことは原則できませんし、借主の地位を他人に譲ることもできません。
このように、その人だからこそ認められる権利は、一身専属的なものとして扱われます。
一身専属的権利の具体例(宅建士試験対策!)
宅建士試験で問われる可能性のある具体的な一身専属的権利の例をいくつか挙げます。
- 扶養請求権(上記参照)
- 生活保護受給権(上記参照)
- 親権:親が子を監護・教育する権利。親でなければ行使できません。
- 遺留分減殺請求権:遺留分を侵害された相続人が、その侵害された部分を取り戻す権利。これは相続人本人が行使するものです。
- 使用貸借における借主の権利(上記参照)
- 組合契約における組合員の地位:組合は組合員同士の信頼関係に基づいて成立するため、原則として組合員の地位を他人に譲渡することはできません。
【ポイント!】 宅建士試験では、「この権利は一身専属的なのか?」という形で問われることがあります。特に、財産権のように「原則として譲渡できる」ものと対比して、「例外的に譲渡できないもの」として一身専属的権利が挙げられることが多いので、注意して学習しましょう。
一身専属的権利ではないもの(比較!)
一方で、多くの権利は「一身専属的ではない」ものとして扱われます。これらは、その権利の内容が個人の属性に強く結びついていないため、他人に譲渡したり、相続させたりすることが可能です。
例:
- 所有権:土地や建物の所有権は、売買や相続によって自由に移動します。
- 債権:お金を貸した際の返還請求権など、債権は原則として譲渡可能です。
- 賃借権:不動産を借りる権利である賃借権は、原則として譲渡・転貸が可能です(ただし、賃貸人の承諾が必要な場合が多いです)。
このように、一般的な財産に関する権利は、一身専属的ではないことが多いです。
まとめ
「一身専属的権利」は、その人自身に強く結びついた、特定の個人しか持ち得ない、または行使できない権利です。宅建士試験では、この概念を理解しているかどうかが問われることがありますので、具体例とともにしっかりと押さえておきましょう。
特に、民法の契約に関する分野や相続の分野で登場することがありますので、条文の読み込みと過去問演習を通して、理解を深めていってくださいね。
今回の解説が、皆さんの宅建士試験合格の一助となれば幸いです!頑張ってください!
一身専属的権利 力だめしクイズ
宅建士試験「権利関係」の重要論点をクイズで確認しよう
力だめしクイズ
学習の成果を試してみましょう。過去問の傾向に基づいたクイズです。準備ができたらスタートボタンを押してください。